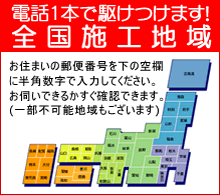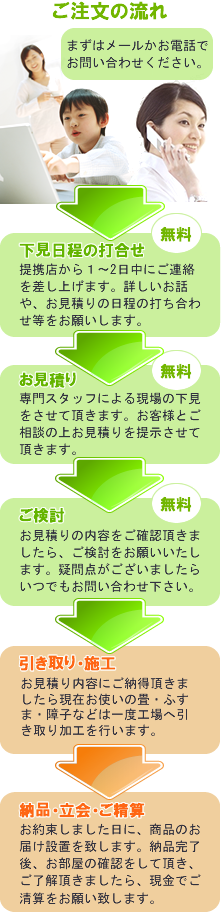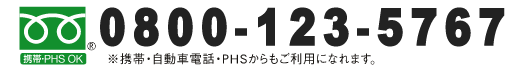ふすまの歴史

襖は8世紀から9世紀の頃、几帳、衝立、屏風、明かり障子など、寝殿造り内部の調度品から、日本独自のものとして生まれてきた。初期の襖は、主に寝間に立てられた寝間障子(襖)である。9世紀末には、中国より唐紙(中国風風俗画)も入り、11世紀頃の襖の奥の上貼りは絹地から既に紙の上貼りに移行し、唐絵から大和絵(日本的風物画)が盛んにになり、襖や屏風に表現され、初期の防寒の役割から室の装飾的要素が加わって、当時の貴族上流社会人の生活に深く関わり定着するようになった。
現時絵物語(1090~1119年)に見える襖絵には、引手が描かれていない。単純に省略したものと言い難いのは、長押や飾り金具類は描いてある事を考慮すると引手は縁に手を掛けて開閉したものと推定される。襖の形式が完成されたのは、平安時代を超え、13世紀鎌倉時代に入ってからと言われている。
や がて、寝殿造りから、15世紀に一休和尚が茶道を確立し、茶室、茶席の襖もその好みに工夫されて、引手に名品が残るまでになった。
がて、寝殿造りから、15世紀に一休和尚が茶道を確立し、茶室、茶席の襖もその好みに工夫されて、引手に名品が残るまでになった。
貴族階級の寝殿造りに対して、武家階級の造った書院造りは16世紀頃に完成したと言われている。特に、安土・桃山時代の頃の襖は、寺院、城郭に絵画芸術の発表の場としての役目をはたしていた。
江戸時代には、京の二条城、桂離宮、日光東照宮など代表的な建築が建造されたが、桂離宮と日光東照宮は、全く対照的な造りであった。日光の豪華壮重に対して、桂離宮は数奇屋風(数奇屋造り)であった。茶道と共に数寄屋造りは住宅様式に入り、江戸幕府の統治下では広く町民階級に普及し、襖絵も絢爛豪華さから淡泊で質素なものへと単純化されて、需要が伸びた。
江戸三百年鎖国の時代に、独自の発展を見た数寄屋造りも、明治の文明開化で欧米風の建築 様式が吹き荒れる中で、襖紙の存在
も危ぶまれた。フェノロサの来日で東洋芸術が昂揚され、襖、屏風、衝立等も日本文化の継承として、建築様式の中にも取り入れられる努力がされた。
様式が吹き荒れる中で、襖紙の存在
も危ぶまれた。フェノロサの来日で東洋芸術が昂揚され、襖、屏風、衝立等も日本文化の継承として、建築様式の中にも取り入れられる努力がされた。
現在の住宅様式の中では、和室の減少や建築構法の変化に伴い襖紙のイメージも大きく変わってきている事も事実である。新しい時代の住宅に合った襖の在り方を創意工夫していく事が、業界発展への課題でもある。
昔の襖柄好みの傾向 |
||||||||||
|